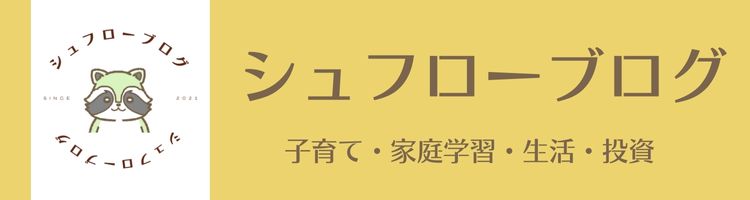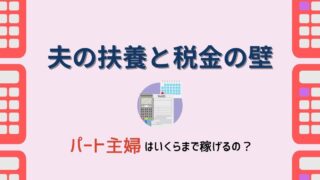夫の扶養内にいる主婦が投資を始めるにあたってまず気になるのが税金のこと。稼ぎたいけど結局負担が増えるのはイヤ!できるだけ支払いが少なくなる範囲で稼ぐにはどうすればよい?
この記事はこんな方におすすめ!
- 「扶養」とは何かピンと来ない
- 扶養内でどれくらい不労所得を得てよいのか知りたい
- 不労所得による収入の税や社会保険料を知りたい
- よく聞く「103万円の壁」や「130万円の壁」とは?
- 損益分岐ポイントを知りたい
稼いだら税金を支払う必要がありますが、夫の扶養されている妻がどれくらい稼ぐとどれくらい税金を支払うことになるのか、ものすごく複雑です…
この記事では、夫の扶養内で投資で稼ぐことを目指していますので、まずは「扶養」とは何か見たあと、よく聞く税金の壁「〇〇円の壁」について解説したいと思います。
※パートなど給与所得がない専業主婦が投資だけの収入を得ることを想定して書いています。夫の扶養内で給与所得のある主婦の場合は以下の記事を合わせてご覧ください♪
「扶養」ってなに?
収入があれば税金などの負担が必要になりますが、扶養する家族がいる場合は、扶養される側(主婦)も扶養する側(夫)も負担が少なくなるようになっています。(※専業主夫の場合は、「主婦」と「主夫」および「妻」と「夫」をそれぞれ入れ替えてお読みください。)
まず、「扶養」の意味を確認しておきます。扶養は、以下の2種類があります。
- 「税制上の扶養」(基礎控除、配偶者控除など)
- 「社会保険上の扶養」(健康保険や厚生年金など)
この2種類の「扶養」で税金や支払いが発生するラインが違う(そして収入の考え方も違う)ため理解するのが難しくなっています。
また、収入(所得)にも種類がいくつかあります。アルバイトやパートは「給与所得」になります。私が取り組んでいる不労所得(FX,CFD,暗号資産)は「給与所得」ではなく、「雑所得」に分類されます。大きな違いは、「給与所得」には「給与所得控除」という控除が55万円あるのに対し、「雑所得」には「給与所得控除」が使えません!48万円の基礎控除のみとなります。
- 給与所得
- パート、アルバイトなど
- 「基礎控除」(48万円)と「給与所得控除」(55万円)の計103万円の控除あり
- 雑所得
- ほとんどの不労所得(FX,CFD,暗号資産)
- 「基礎控除」(48万円)のみ
つまり、
不労所得(雑所得)の場合は、「〇〇万円の壁」という税金の壁はアルバイトやパートをしている場合と少し異なります。
この記事では、よく言われる「〇〇万円の壁」ごとに、【主婦(被扶養者)の負担】と【夫(扶養者)の負担】がどのように変わるかを見ていきます。ただし、主婦の収入は、FX等の雑所得に分類されるもののみである場合についての記述になります。
「〇〇円の壁」の全体像
まずは、「〇〇円の壁」を超えるとどうなるか、表にまとめました。(注:この表は雑所得のみの収入の場合です。)それぞれの壁ごとに詳しく手取りの変化を見ていきます。
| 負担者 | 主婦(被扶養者) | 主婦(被扶養者) | 夫(扶養者) | 夫(扶養者) | ||
| 壁の種類 | 不労所得額 | (A) 不労所得への課税 | (B) 社会保険料の負担 | (C) 夫の配偶者控除 | (D) 夫の配偶者手当※ | |
| ① | ー | 48万円以下 | 支払なし | 支払なし | 配偶者控除あり | 支給される |
| ② | 48万円の壁 | 48万~95万 | 所得税 住民税 | 支払なし | 配偶者特別控除あり(満額) | 支給される |
| ③ | 95万円の壁 | 95万~103万 | 所得税 住民税 | 支払なし | 配偶者特別控除あり(減額) | 支給される |
| ④ | 103万円の壁 | 103~106万 | 所得税 住民税 | 支払なし | 配偶者特別控除あり(減額) | 支給される |
| ⑤ | 106万円の壁 | 106~130万 | 所得税 住民税 | 支払なし | 配偶者特別控除あり(減額) | 支給される |
| ⑥ | 130万円の壁 | 130万超 | 所得税 住民税 | 社会保険の支払い | 控除なし | 支給されない |
※公務員の場合。会社によって制度が異なります。
収入が48万円を超えると、主婦の側に所得税や住民税の支払いが必要になります。
収入が95万円を超えると、夫の配偶者控除が少しずつ減っていきます。
収入が130万円を超えると、主婦の側に所得税・住民税に加えて、社会保険料の支払いが必要となり、また夫の配偶者控除や配偶者手当もなくなってしまいます。

では、それぞれの収入でかかる税金をみていこう!
「〇〇円の壁」の詳細
主婦の不労所得(雑所得収入)の額により、税負担や夫の手取りにどのように影響を与えるか見ていきましょう♪
① 48万円以下
主婦の不労所得(雑所得)が48万円以下だった場合。
主婦の負担
- なし
夫の負担
- なし
まず、主婦自身の基礎控除である48万円が一つ目の基準になります。基礎控除とは、「確定申告や年末調整において所得税額の計算をする場合に、総所得金額などから差し引くことができる控除の一つ」です。
2020年1月から税金に関する制度が変更され、「基礎控除」は「10万円引き上げられ48万円」となりました。(ただし、年間所得が2,400万円以下の場合。改正前は所得金額に関わらず一律年間38万円の基礎控除。)【参考:No.1199 基礎控除|国税庁 – 所得税】

夫の扶養範囲内で不労所得を目指す主婦にとってはラッキーですね!
この範囲内であれば、所得税の確定申告は不要です。住民税については、お住いの市区町村によって申告が必要となる場合があるようです。(ちなみに、私の居住地では非課税であっても申告してほしいと言われました。)
また、夫の側にも配偶者控除が適用されます。控除額は夫の所得額により異なります。
| 年間所得額 | 配偶者控除額 |
|---|---|
| 900万円以下 | 38万円 |
| 900万~950万円 | 26万円 |
| 950万~1,000万円 | 13万円 |
| 1,000万円超 | なし |
【参考:No.1191 配偶者控除|国税庁】
☆まとめ☆
48万円以下の収入であれば、主婦・夫ともに税金など新たな負担はありません
② 48万円の壁~95万円まで
主婦の負担
- 所得税・住民税
夫の負担
- なし
主婦の負担について
まず、上で述べたように基礎控除である48万円が一つ目の基準になります。これを超えると、主婦の側に所得税と住民税の支払い義務が発生します。また、確定申告が必要になります。
同じ雑所得でも、投資の種類によって税金のかかり方が異なります。
- 申告分離課税:株、FX、CFDなど
- 総合課税:暗号資産など
申告分離課税
- 株、FX、 CFDなど
- 税率:20.315%(所得税 15%、住民税 5%、復興特別所得税 0.315%)
- 収入金額にかかわらず一定の税率がかかります。
【参考:No.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係|国税庁】
【参考:No.1522 先物取引に係る雑所得等の課税の特例|国税庁】
総合課税
- 暗号資産など
- 収入金額に応じて違う税率となります。所得税と住民税は以下のようになります。
【参考:No.1524 暗号資産を使用することにより利益が生じた場合の課税関係|国税庁】
☆所得税
以下の税率になります。95万円以下でしたら所得税率は5%ですので、申告分離課税よりも安くなります。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円超 | 40% | 2,796,000円 |
※ 平成25から平成49までの各年分の確定申告においては、所得税と復興特別所得税(原則としてその年分の基準所得税額の2.1%)を併せて申告・納付することとなります。
☆住民税
典型的には、所得割(10%)と均等割(5,000円程度)の合計になります。お住まいの地域によって異なりますので、詳細はご自身の住所地でご確認ください。
夫の負担について
夫の年間所得額が1,000万円以下であれば、配偶者特別控除を受けられます!ただし、妻の収入および夫の年間所得金額によって配偶者特別控除額が異なります。
主婦の所得95万円までは、配偶者控除と同額の配偶者特別控除があります!
| 夫の年間所得金額 | |||
| 妻の収入 | 900万円以下 | 900万~950万円 | 950万~1,000万円 |
| 48万~95万円 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
| 95万~100万円 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
| 100万~105万円 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
| 105万~110万円 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
| 110万~115万円 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
| 115万~120万円 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
| 120万~125万円 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
| 125万~130万円 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
| 130万~133万円 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
【参考:No.1195 配偶者特別控除|国税庁 – 所得税】
☆まとめ☆
主婦の収入(雑所得のみの場合)が48万円~96万円の場合
- 所得税と住民税の支払いが必要(主婦)
- 確定申告が必要(主婦)
- 夫は配偶者控除と同額の控除(配偶者特別控除)があるため、夫の負担はなし
- 税金の支払いの分だけ手取りが減ることになりますが、稼ぐと損をするという逆転現象はありません。
③ 95万円の壁~103万円まで
主婦の負担
- 所得税・住民税
夫の負担
- 配偶者特別控除の減額(表4の通り)
主婦の負担について
「② 48万円の壁~95万円まで」で書いた所得税・住民税の支払いが必要です。
夫の負担について
主婦の収入が95万円を超えると、上の表4に示されているように配偶者特別控除が段階的に減っていきます。
☆まとめ☆
主婦の収入(雑所得のみの場合)が95万円~103万円の場合
- 所得税と住民税の支払いが必要(主婦)
- 確定申告が必要(主婦)
- 夫は配偶者特別控除が減り、その分の所得税・住民税が増加
- 95万円を超えると、世帯としての収入は増えにくくなるが、稼ぐと損をするという逆転現象はありません。
④ 103万円の壁~106万円まで
主婦の負担
- 所得税・住民税
夫の負担
- 配偶者特別控除の減額(表4の通り)
☆「103万円の壁」とは?
103万円の壁は、アルバイト・パート(給与所得)のみで働く主婦が税金(所得税・住民税)を支払うようになるポイントのことですので、不労所得(雑所得)のみの場合は特に意識する必要はありません。「③ 95万円の壁~103万円」と同じ条件になります。
参考までに、給与所得の場合は、基礎控除(48万円)に加えて、給与所得控除(55万円)がありますので,あわせて103万円までは非課税です。そのため、給与所得者にとっては税金支払いの必要が生じるという意味で重要なポイントとなっています。

パートをしている主婦の間で一番よく耳にするのが、この103万円の壁かな。
年末になると『103万超えそうなので、シフト減らしてください・・・』という声を聞いたことがある人も多いのでは?
☆まとめ☆
主婦の収入(雑所得のみの場合)が103万円~106万円の場合
「③ 95万円の壁~103万円」と同じです。つまり、
- 所得税と住民税の支払いが必要(主婦)
- 確定申告が必要(主婦)
- 夫は配偶者特別控除が減り、その分の所得税・住民税が増加
- 95万円を超えると、世帯としての収入は増えにくくなるが、稼ぐと損をするという逆転現象はありません。
⑤ 106万円の壁~130万円まで
主婦の負担
- 所得税・住民税
夫の負担
- 配偶者特別控除の減額(表4の通り)
☆「106万円の壁」とは?
106万円の壁は、アルバイト・パート(給与所得)のみで働く主婦が所定の条件を満たす場合に、主婦が雇用先の社会保険(健康保険、介護保険、厚生年金)に加入するポイントです。つまり、夫の社会保険の扶養から外れてしまい、主婦が自分で支払う可能性が出てきます。不労所得(雑所得)のみの場合は特に意識する必要はありません。
参考までに、所定の条件とは・・・
- 週の所定労働時間が20時間以上あること
- 雇用期間が1年以上見込まれること
- 賃金の月額が8.8万円以上であること
- 学生でないこと
- 特定適用事業所または任意特定適用事業所に勤めていること(国、地方公共団体に属する全ての適用事業所を含む)
【参考:適用事業所と被保険者|日本年金機構】
仮に給与収入が年収108万円(月9万円)で所定の条件にかなう場合、年間約18万円の社会保険料が必要となり、年収103万円の場合よりも手取りが少なくなってしまうという逆転現象が生じてしまうことがあります。不労所得の場合、この壁を気にしなくてよいのは大きいですね。
☆まとめ☆
主婦の収入(雑所得のみの場合)が106万円~130万円の場合
「③ 95万円の壁~103万円」「④ 103万円の壁~106万円」と同じです。つまり、
- 所得税と住民税の支払いが必要(主婦)
- 確定申告が必要(主婦)
- 夫は配偶者特別控除が減り、その分の所得税・住民税が増加
- 95万円を超えると、世帯としての収入は増えにくくなるが、稼ぐと損をするという逆転現象はありません。
⑥ 130万円の壁以降
主婦の負担
- 所得税・住民税の支払い
- 社会保険料の支払い(年間18万円以上)
夫の負担
- 配偶者手当がなくなる(私の夫の場合は、年額78,000円の手取り減)
- 配偶者特別控除がなくなる(控除額38万円、税率20%だと年額換算76,000円の負担増)
主婦の負担について
主婦の年収が130万円を超えると「社会保険上の扶養」(健康保険、介護保険、厚生年金)から外れます。つまり、第3号被保険者ではなくなってしまい、自分で社会保険に加入する必要があります。
ここで注意しないといけないのは、「社会保険上の扶養」における年収と、所得税などの「税制上の扶養」における年収の考え方がまったく違うので要注意です。
具体的な計算方法は、加入する社会保険制度により異なるようです。私の夫(公務員)が加入する社会保険制度は以下のようになっています。
「収入とは所得税法上の所得(暦年でいう1月~12月までの所得額)をいうものではなく、収入事由が発生した日から12ヶ月間における収入額となります。(どの月を基準にしても年額130万円未満でなければ被扶養者として認められません。)」
公務員社会保険制度規約より
つまり、どの月の収入も108,333円以下でなければならないということです。ある月の収入が多すぎたから、年末に調整…というのは通用しないようです。
また、収入には幅広い収入含まれるようです。
「給与収入(交通費などの非課税収入及び賞与を含む)、年金(個人年金含む)、恩給、雇用保険、利子収入、不動産収入、健康保険法及び労災保険法による休業補償費等、実質的に収入と認められるものが対象となります。」
公務員社会保険制度規約より
もし夫の社会保険上の扶養を外れて自分で社会保険料を支払う場合、収入にもよりますが年間18万円以上は必要となるようです…
夫の負担について
私の夫の場合は、この社会保険上の130万円の壁が、配偶者手当の支給(月額6,500円)とも連動しているのです。つまり、私の収入が130万円を超えると、夫の手取りは年間78,000円(6,500円×12か月)下がることになってしまいます。
さらに、配偶者(特別)控除もなくなってしまいます。控除額は38万円ですので、税率20%と考えると所得税だけで年額換算76,000円の負担増という計算になります。

130万円までは、稼いだ金額にかかる税金だけを気にすればよかったけど、130万円以上を稼いでしまうと、社会保険料を自分で支払わなければいけなくなって、逆に手取りが減ってしまうことがあるんだね。
世帯全体で見考えると、私(主婦)が130万円以上稼ぐことにより、ざっと年額33万円以上手取りが低下することになり、130万円ぎりぎりに収めた場合に比べて、かなり手取りが少なくなってしまいます。
大まかに見積もって、年収170万円稼ぐことでやっと年収130万円のときの手取りと同じくらいになりそうです。
年収130万(月収108,333円)をわずかに超えそうな場合は損切りなどをしてこの収入内に抑えるのがよさそうです。
年収130万を超えるのであれば、170万円以上を目指すようにしたいと思います。
☆まとめ☆
主婦の収入(雑所得のみの場合)が130万円を超えると
- 所得税・住民税の支払いが必要になる
- 社会保険料で18万円以上かかる
- 夫の配偶者特別控除がなくなる
- 夫の配偶者手当がなくなる(勤務先により異なる)
まとめ
ここまで専業主婦が夫の扶養内で投資などの不労所得のみで稼ぐときの税金について見てきました。

税金や社会保険料の支払いは痛いけど仕方ないこと。投資計画のご参考になれば幸いです!